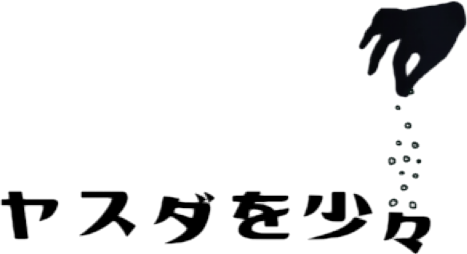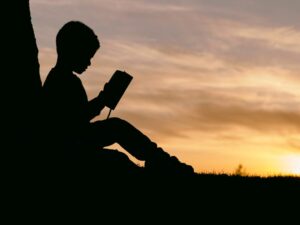愛発越〜水坂峠(ポイント0~12)
愛発越から水坂峠までのコースタイムは以下の通りです。
このコースタイムは公式ガイドブックを参考にしており、登山経験中級者5名程度のグループで、春、秋のコンディションが良い日の日帰り装備の設定です。
装備の重さや天候等でコースタイムは大きく変わりますのであくまでも参考程度とお考え下さい。
| ポイント/標高 | コースタイム |
|---|---|
| 0.愛発越(あらちごえ) /390m | |
| 1.乗鞍岳(のりくらだけ) /865.2m | 2時間10分(愛発越から) |
| 2.黒河峠(くろことうげ)/570m | 2時間40分(乗鞍岳から) |
| 3.三国山(みくにやま)/876.3m | 1時間(黒河峠から) |
| 4.明王の禿(みょうおうのはげ)/780m | 25分(三国山から) |
| 5.赤坂山(あかさかやま) /823.8m | 25分(明王の禿から) |
| 6.粟柄越(あわがらごえ) /770m | 10分(赤坂山から) |
| 7.寒風(かんぷう) /853.8m | 1時間20分(粟柄越から) |
| 8.大谷山(おおたにやま)/813.9m | 40分(寒風から) |
| 8-1.抜土(ぬけど) /570m | 45分(大谷山から) |
| 9.大御影山(おおみかげやま)/950.1m | 1時間50分(抜土から) |
| 10三重嶽(さんじょうがだけ) /974.1m | 1時間40分(三重嶽(から) |
| 11.武奈ヶ嶽(ぶながだけ)/865m | 2時間30分(武奈ヶ嶽から) |
| 12.水坂峠(みさかとうげ)/280m | 2時間10分(水坂峠から) |
愛発越(あらちごえ)

国境バス停はすなわち国境高原スノーパークの入り口になります。


スタート地点となる愛発越はシーズンオフで閉まっているゲートを越えた所にありますのでゲートを脇からすり抜けるといよいよ高島トレイルのスタートです。
愛発越(あらちごえ) 〜 乗鞍岳(のりくらだけ)



愛発越から乗鞍岳まではコースタイムで2時間10分。
愛発越をスタートしそのままスキー場に向かって進み、ひたすらスキー場のゲレンデを登っていきます。
リフトの終点を目指しましょう。


リフトの終点から山に向かって右側へ進むと高島トレイルの標識が見え、登山口があるのでそこから山へ入ります。
これからの長い道のりでこの標識と黄色のテープをたどりながらゴールを目指します。


それなりのアップダウンを繰り返しながら中間地点の目印となる鉄塔を目指します。


途中、高島トレイルの標識が無くなってただのポールになっている分かれ道(写真左)がありますが、左に見える黄色のテープの方に進みます。
四角い建物の手前に立っているのが一つ目の目的地乗鞍岳です。
乗鞍岳(のりくらだけ) 〜 黒河峠(くろことうげ)

乗鞍岳から黒河峠まではコースタイムは160分 (2時間40分)と少し長い距離を歩くことになります。

乗鞍岳を出発すると大きな電波棟が現れ、それを左に見ながら進みます。


ブナ林を抜け、さらに進んで芦原岳まで登ると右手に敦賀湾、左手には琵琶湖が見えるきれいな景色が広がります。
この芦原岳付近でちょうど中間地点ぐらいです。

黒河峠到着。
黒河峠は登山道の入り口でもあり、高島トレイルのルート上で唯一トイレがある場所でもあります。
この先はゴール地点の桑原橋までトイレはありません。
黒河峠(くろことうげ) 〜 三国山(みくにやま)

三国山まではコースタイムで1時間です。
黒河峠570mから三国山876.3mまでをぐんぐん登っていく登りメインのルートになりますので、水分の消費が気になるところ。


道中は手軽に補給できる水場がいくつかありますので、ここで一旦補給することをおすすめします。

三国山付近には4月1日の時点でかなりの残雪がありました。
深い所では膝まで埋まる程の雪が残っており、この残雪の影響がかなりのロスタイムになりました。
自身のリサーチ不足と準備不足が招いた結果ではありますが最終水坂峠で下山を決意した理由の一つがこのタイムロスでした。
もし春先に高島トレイルに挑戦する方は雪が溶けた5月以降が良いと思います。
私たちは初日から残雪の洗礼を受けて精神的、肉体的にも疲れてので明王の禿にの手前でテントを張ってこの日は休むことにしました。
三国山(みくにやま) 〜 明王の禿(みょうおうのはげ)

三国山から明王の禿まではコースタイムで25分。
二日目、私たちは引き続き残雪に足を取られたり、雪を避けながら少しルートから外れなが進んだので1時間以上はかかりました。

道中豊富な水場がありました。


残雪ゾーンを抜けると景色が一変し、岩肌がゴツゴツと露出した明王の禿が現れした。
この地点にも残雪があればこの時点で下山をするつもりでしたが、全く雪は無く見事な景色が広がったので進むことを決意しました。
明王の禿(みょうおうのはげ) 〜 赤坂山(あかさかやま)

明王の禿から赤坂山まではコースタイム25分。
Vの字に一度下ってから直ぐに登るコースで、開けた景色が気持ちいいです。


赤坂山から見る景色は絶景です。
そして赤坂山と言えば通称「ネコ耳鉄塔」(写真右)が象徴的です。
赤坂山(あかさかやま) 〜 粟柄越(あわがらごえ)

赤坂山を下った所が粟柄越で、コースタイム10分のショートコース。

直ぐ近くにネコ耳鉄塔が建っています。
粟柄越(あわがらごえ) 〜 寒風(かんぷう)

粟柄越から寒風まではコースタイム1時間20分。

この辺りは日本海側からの季節風の影響で大きなが木が育たないため気持ち良い草原の稜線が続きます。
ここ以降はだんだん森の中に入っていくので、この辺りが景色を楽しむ上では一番だと思います。

寒風から見る景色。
琵琶湖が一望できる絶景スポットです。
寒風(かんぷう) 〜 大谷山(おおたにやま)

寒風から大谷山まではコースタイム40分。
途中の写真はありませんが寒風から一旦下って森の中を抜け、開けた場所に出るのでそこを登りきった所が大谷山です。

寒風同様に景色が最高です。
大谷山(おおたにやま) 〜 抜土(ぬけど)

大谷山から抜け土までのコースタイムは45分。
基本的には森歩きになり、下が多めのルートになります。
この辺りから一般登山者があまり多く通らなためか、登山道らしきものが目視で確認しずらくなってきます。

また、途中石がゴツゴツした場所があり、そこの分岐付近にこの黄色のテープがありましたが、よく見ると何も書いておらずこれは高島トレイルのテープではないです。
私は何も迷いもなくこのテープの方に進んでしまい、しばらくしてからYAMAPを見て気付き引き返しました。


急な下り坂を下きった所が抜け土です。
近くに豊富な水場があるので久しぶりの水分補給ができます。
この先は水坂峠まで水場が無く、高島トレイル全行程で水場が無い最も長い区間になります(コースタイム9時間10分)
当然背負うことが出来る水の重さには限りがありますが、出発前に満タンにしておき、水の消費バランスを考えながら進むようにしましょう。
抜土(ぬけど) 〜 大御影山(おおみかげやま)

抜け土から近江坂を通って大御影山までコースタイムで1時間50分。
抜け土からトレイルに戻るといきなり強烈な急登になります。
そしてあまり誰も歩いていないせいか、草木がトレイル上に覆いかぶさるように生えており、藪漕ぎをしながら歩く所がたくさんあります。
そして予想はしていましたが、、、、

藪漕ぎをする度に足や靴にマダニがくっ付いてきます。
多い時では「1藪漕ぎ8マダニ」でした。
もし短パンで歩くつもりをされているのであれば考え直した方が良いですし、私は持って行かなくで後悔しましたのでみなさんは絶対にマダニ避けスプレーを持参しましょう。

大御影山からは今まで歩いてきた大谷山、寒風、赤坂山が見えます。

そして反対側には今から向かう三重獄が見えます。
この時点で既に残雪が確認でき、三国山付近の悪夢が頭をよぎります。
大御影山(おおみかげやま) 〜 三重嶽(さんじょうがだけ)

大御影山から大日尾根を通り三重嶽まではコースタイム1時間40分。
大御影山から一旦下って大日尾根に登った辺りから所々残雪が現れ、更に登るとルート上の少し掘れた所のみに雪が残っている状態になりました。


何度か足が埋まることで靴が濡れはじめたので、雪を避けるためにルートを際を藪漕ぎながら歩くとマダニがくっ付いてきます。
「雪→避ける→ダニ」の繰り返し。

なかなかカオスな状況を切り抜けて何とか三重嶽に到着したのが17時半。
予定ではまだまだ先に進む予定でしたが、残雪とマダニとの格闘で疲れたのと、公式ではこの先は迷い道が多いルートとのことだったので暗くなる前にこの付近でテントを張ることにしました。
三重嶽(さんじょうがだけ) 〜 武奈ヶ嶽(ぶながだけ)

三重獄から武奈ヶ嶽まではコースタイム2時間30分。
先述しましたが、三重嶽から先は迷い道が多いルートが続きます。

目視で確認できる道らしい道がなく、黄色テープも見当たらない場所が多いためYAMAPなどの地図アプリでGPSを頼りに進みます。
登り降りを繰り返しながら進むと予報通り雨が降り始めました。
事前に天気予報は確認していたのでレインウエアを(私はポンチョ)羽織って進みましたが予想外だったのが強風でした。

容赦なく吹き付ける風にバタバタと靡くポンチョに後悔しながら進みます。

道中木を伝って落ちてくる雨水に歓喜しながらありがたく補給させていたきました。

ポンチョを靡かせて武奈ヶ嶽到着。
武奈ヶ嶽(ぶながだけ) 〜 水坂峠(みさかとうげ)

武奈ヶ嶽から水坂峠まではコースタイムは2時間10分。
とにかく厳しい下が続きます。

途中で何度か「え?これルート合ってる?」と言ってしまうぐらいの滑り台のような角度の下り坂を下ります。
標高865mのから標高280mまで一気下るので低い木がメインだった景色が一変して真っ直ぐ伸びた杉林に変わります。

水坂峠はポイント裏に流れる沢も含めて水が豊富なので抜け土以来の久々の補給ができます。

続いてニの谷山へ進みましたが途中で雨風がさらににキツくなってきたのと、この時点で登山計画のタイムからかなり遅れていたため、このまま進むべきかどうかを悩んだ末に水坂峠まで戻って下山することを決意しました。
でも必ずリベンジしますので、この先のルートに関してはその後とさせて頂きます。